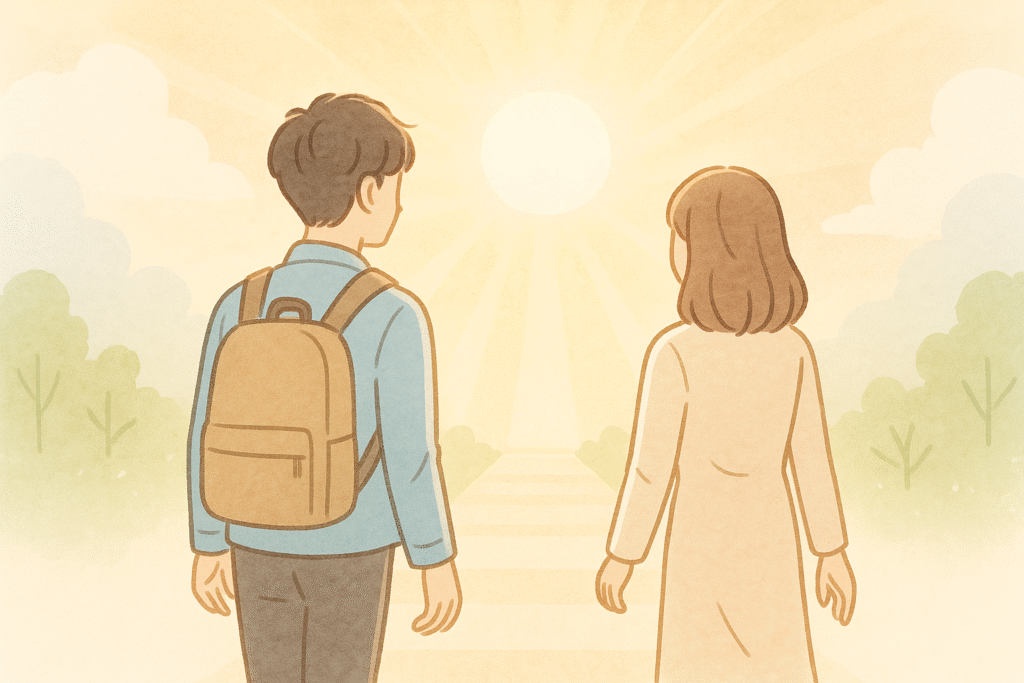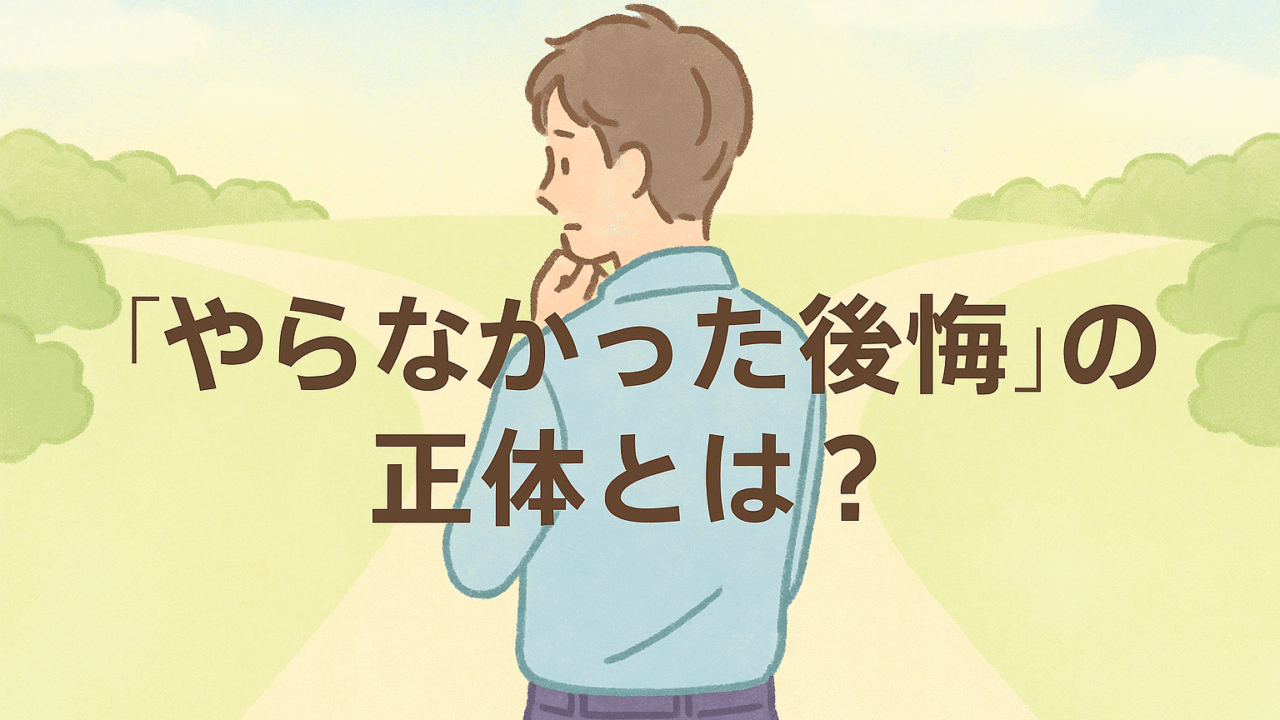「もしあのとき、一歩を踏み出していたら──」
そんな思いが、ふとした瞬間に胸をよぎったことはありませんか?
転職、恋愛、学生時代の挑戦、人間関係で伝えられなかった言葉。
人生には数えきれないほどの選択がありますが、その中で特に心に強く残るのが 「やらなかった後悔」 です。
心理学者トーマス・ギロヴィッチとビクトリア・メディベの研究(1995年)によると、長期的に残る後悔の約8割は「やらなかったこと」に関するもの であると報告されています。
短期的には「やって失敗した後悔」の方が強いのですが、時間が経つにつれて薄れていきます。失敗や恥ずかしさは「経験」として整理できるからです。
しかし、「やらなかった後悔」は違います。
挑戦しなかったことで「もう一つの未来」を試すことができず、想像の中で理想化された“もしもの自分”と今の自分を比べ続けてしまう。
たとえば、学生時代に留学を諦めた人は、社会人になってからも「もし行っていれば、今とは違うキャリアや出会いがあったのでは」と思い続けます。
告白できなかった恋は、何年経っても「あのとき想いを伝えていれば…」と心に残り続けるのです。
このように「やらなかった後悔」は、挑戦できなかった自分を責める感情と、「もう取り返しがつかない」という喪失感が重なり、静かに、しかし確実に未来の自分を苦しめます。
では、なぜ人は「やらなかったこと」をこれほどまでに後悔するのでしょうか?
その理由は、私たちの心理に深く根ざした 損失回避 や 現状維持バイアス、そして 選択のパラドックス といった心理的なパターンにあります。
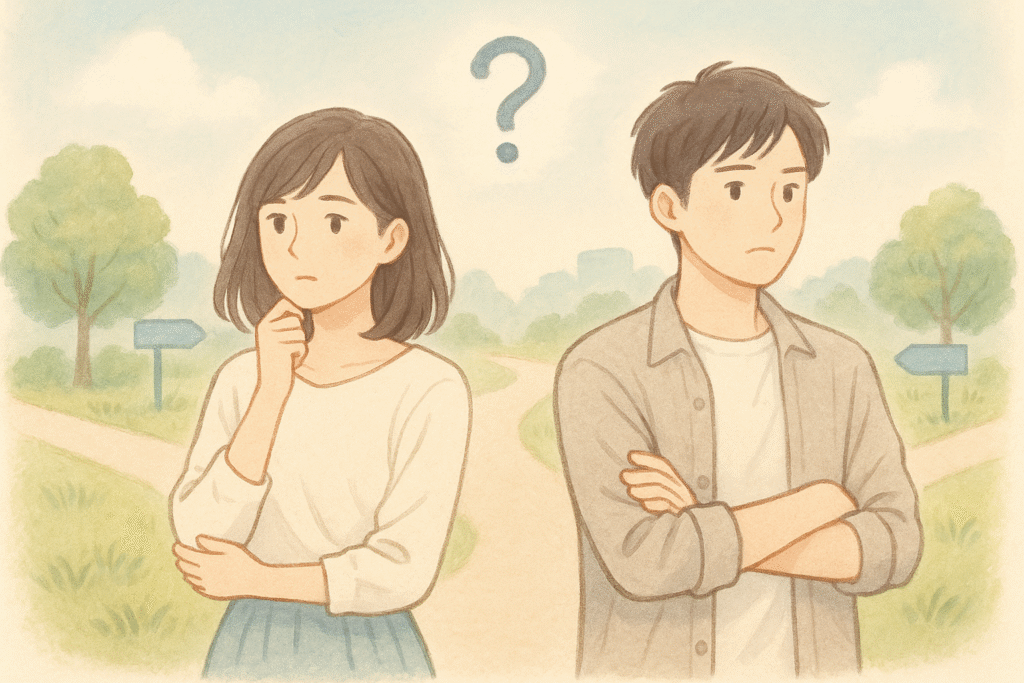
この記事では、心理学的な研究や実際の事例を交えながら「やらなかった後悔」の正体を解き明かし、どうすれば後悔を減らし、自分の選択を信じて生きられるのかを一緒に考えていきます。
Contents
第1章:やらなかった後悔とは何か
私たちは日々、さまざまな選択を繰り返しています。
転職するか、このまま今の仕事を続けるか。
告白するか、気持ちを胸に秘めておくか。
挑戦するか、安全な道を選ぶか。
その中で、人が特に心に強く残す後悔が 「やらなかった後悔」 です。
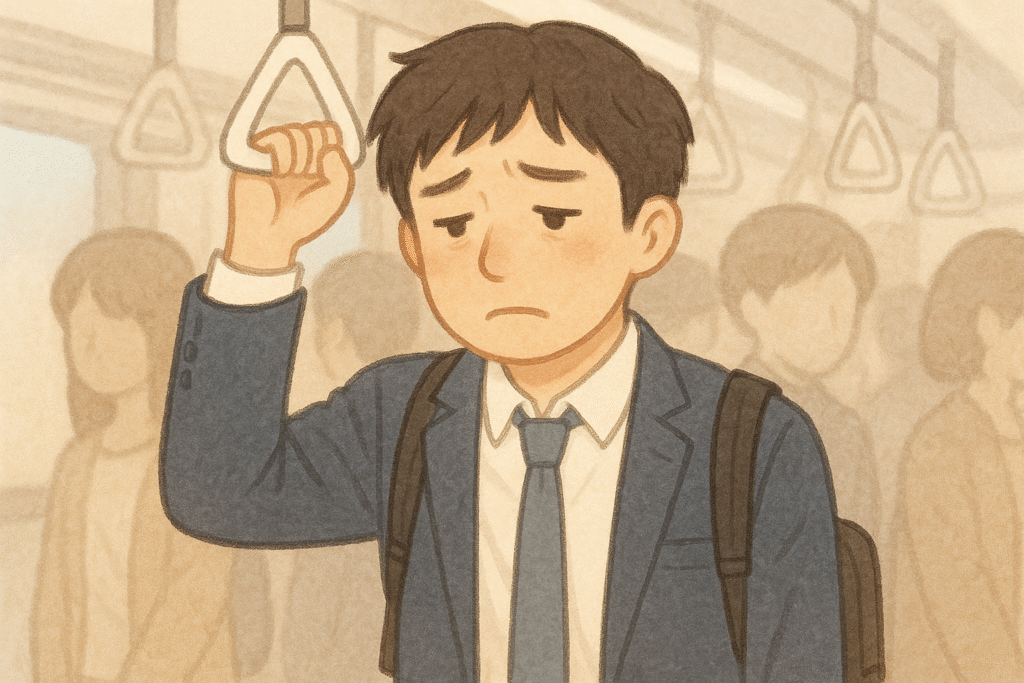
やった後悔とやらなかった後悔の違い
心理学者トーマス・ギロヴィッチとビクトリア・メディベの研究(1995年)は、後悔には時間的な特徴があることを示しました。
- 短期的には「やった後悔(行動して失敗した後悔)」の方が強く感じられる
- 長期的には「やらなかった後悔(行動しなかった後悔)」が強く残りやすい
たとえば、失敗したプレゼンや、上手くいかなかった面接を思い出すと、その瞬間は顔から火が出るような恥ずかしさに襲われます。これが「やった後悔」です。
しかし時間が経つと、その経験は「いい勉強になった」「あの失敗があったから今の自分がある」と整理されやすくなります。転職で失敗しても、新しいスキルや人脈を得られたと考える人は少なくありません。恋愛で振られたとしても、「自分の気持ちを伝えられた」ことで前に進めたと感じられることもあります。
一方で「やらなかった後悔」は違います。
「挑戦しなかった」「伝えなかった」「動けなかった」── その選択には修正の余地がなく、頭の中に「もしやっていれば、別の未来があったのでは?」という想像を残し続けてしまうのです。
実際によくある「やらなかった後悔」
- 学生時代の挑戦
- 留学に行きたかったけれど不安で諦めた
- 部活でレギュラーを目指さなかった
- 好きな人に気持ちを伝えられなかった
- 社会人になってからの選択
- 転職を考えたが、結局動けなかった
- 起業に挑戦したいと思いながら、安定を捨てられなかった
- 新しい資格やスキル習得を先延ばしにした
- 人間関係における後悔
- 親に感謝を伝えられなかった
- 大切な人に素直になれなかった
これらは一見「小さな選択」に見えるかもしれません。
しかし時間が経つと、「あのとき行動していれば今とは違う人生だったかもしれない」という未練へと変わり、何年も尾を引く大きな後悔に育ってしまうのです。
「やらなかった後悔」はなぜ重いのか
やった後悔には「修正」や「学び」があります。失敗から得られる経験は、次の挑戦につながります。
一方、やらなかった後悔は「別の未来を想像し続ける」特徴があります。人は過去を振り返るとき、良い方向に理想化してしまう傾向があり、「もし挑戦していたら、きっと成功したに違いない」と考えてしまうのです。
そのため、やらなかった後悔は時間が経つほど大きく膨らみ、心に重くのしかかります。
👉 この第1章を読みながら、あなた自身も「やらなかった後悔」を一つ思い浮かべてみてください。きっと心の奥にまだ残っているはずです。
第2章:心理学から見る「やらなかった後悔」
「やらなかった後悔」は、単なる偶然ではなく、私たちの心理的な傾向から生まれています。ここでは代表的な心理学的要因を4つ紹介します。

1. 損失回避(Loss Aversion)
行動経済学で有名なカーネマンとトヴェルスキーの研究によると、人は「得る喜び」よりも「失う恐怖」を約2倍強く感じることが示されています。
これは「プロスペクト理論」と呼ばれ、ノーベル経済学賞の受賞理由にもなった発見です。
- 月収が5万円増える喜びより、月収が5万円減る不安の方が強い
- 転職してキャリアアップする希望より、「今の安定を失うかもしれない」という恐怖が勝つ
この損失回避の心理が、私たちを「挑戦」から遠ざけ、結果として「やらなかった後悔」へと導いてしまうのです。
2. 現状維持バイアス
人間には「変化するより、現状のままが安心」と感じる性質があります。
これを現状維持バイアスと呼びます。
- 気に入らない上司がいても「今の会社の方が安全」と思って動かない
- 人間関係がうまくいかなくても「ここを離れたらもっと大変かも」と不安になる
たとえ今の環境に不満があっても、「変化=リスク」と考えてしまうため、新しい挑戦を逃しやすいのです。
3. サンクコスト効果
「今まで費やしてきた時間や労力がもったいない」と感じる心理です。
- 10年間勤めた会社を辞められない
- 長く付き合った恋人に不満があっても別れられない
- 何十時間も遊んだゲームを「やめるのはもったいない」と思う
過去に投資したものにしがみつくあまり、新しい一歩を踏み出せなくなる。
そして気づけば「なぜもっと早く決断しなかったのか」と後悔を積み重ねてしまうのです。
4. 選択のパラドックス
心理学者バリー・シュワルツが提唱した「選択のパラドックス」も重要です。
選択肢が多いほど自由になれるように思えますが、実際には逆で「決められない」「選んだ後に後悔する」心理が働きます。
有名な実験では、スーパーで「6種類のジャム」を並べた場合と「24種類のジャム」を並べた場合を比較しました。
試食は24種類の方が多かったのに、実際に購入に至った割合は6種類の方が圧倒的に高かったのです。
現代の私たちはまさにこの状態。
転職サイトを開けば無数の求人、SNSを見れば無限の生き方。
選択肢が増えすぎた結果「どれが正解かわからない」と迷い、結局動けなくなるのです。
読者への問いかけ
あなたにも「迷いすぎて動けなかった」経験はありませんか?
- 就職先を選ぶとき
- 恋人との関係を続けるか迷ったとき
- 転職や副業を考えたとき
そのとき選んだ「安全策」が、いま心の中で重荷になっていないでしょうか。
✨ 小まとめ
これらの心理はすべて「人が行動できなくなる理由」とつながっています。
損失を恐れ、現状にしがみつき、過去に縛られ、選択肢に迷う──。
こうして人は「やらなかった」という選択を取りがちであり、その積み重ねが「長く残る後悔」を生み出してしまうのです。その積み重ねが「長く残る後悔」を生み出してしまうのです。
第3章:実際によくある「やらなかった後悔」
心理学的な要因を理解したところで、実際にどのような「やらなかった後悔」が多いのかを見ていきましょう。
人生のあらゆる場面で、私たちは小さな決断を先送りし、その結果が大きな後悔に育ってしまうことがあります。
学生時代に多い後悔
「留学したかったけど、英語力に自信がなく諦めた」
「部活でレギュラーを目指さなかった」
「好きな人に告白できなかった」
学生時代の後悔は、その後の人生でも何度も思い出されます。
特に若い頃の挑戦は「人生の分岐点」となりやすく、行動しなかったことが何十年経っても心に残るのです。
留学を諦めた人は、社会人になってから「もし行っていたら、今とは違うキャリアや出会いがあったのでは」と考えます。
告白できなかった恋は、時間が経つほどに理想化され、「もし想いを伝えていたら…」という幻想となって残り続けます。
社会人になってからの後悔

「転職を考えたけど、結局動けなかった」
「起業や副業をしたかったが、安定を捨てられなかった」
「新しいスキルに挑戦せずに、キャリアを停滞させてしまった」
社会人になると、責任や環境の制約が増え、挑戦を避けやすくなります。
しかしキャリアの分岐点で動けなかったことは、後からじわじわと重みを増していきます。
たとえば、30代のうちに転職をしなかった人が、40代になって求人条件の「年齢制限」に直面し、初めて「もっと早く行動していれば」と痛感するケースも少なくありません。
また、新しいスキル習得を先延ばしにした結果、同僚や後輩に追い抜かれ、自信を失うこともあります。
人間関係における後悔
「親に感謝を伝えられなかった」
「大切な人に素直になれなかった」
「謝る勇気を持てなかった」
人間関係の後悔は、相手がいなくなった後では取り返しがつきません。
たとえば、親に「ありがとう」と言えなかった人は、親を亡くした後に「どうしてあのとき言葉にしなかったのだろう」と一生悔やむことになります。
恋人や友人に謝れなかった人も、関係が途絶えたあとで「たった一言で違う未来になったのでは」と考えてしまうのです。
読者への問いかけ
これらの例の中に、自分の経験と重なるものはありませんか?
大抵の後悔は、そのときには「小さな選択の先送り」に見えます。
しかし、時間が経つとそれは「大きな分岐点」へと変わり、何年も心を縛り続ける後悔となるのです。
✨ 小まとめ
「やらなかった後悔」は、学生時代・社会人・人間関係と、人生のあらゆる場面で生まれます。
そのときは「小さな選択の先送り」に過ぎないように思えても、時間が経つにつれて「大きな分岐点だった」と気づかされるのです。
そしてその後悔は、学びや修正が効く「やった後悔」と違い、想像の中で何度も繰り返されるため、長く心に残り続けます。
第4章:調査データから見る「やらなかった後悔」
ここまで「やらなかった後悔」の心理的背景や具体例を見てきました。
では実際に、どれほど多くの人が「やらなかった後悔」を経験しているのでしょうか?
いくつかの調査データを紹介します。

1. 転職に関する後悔
リクルートワークス研究所の調査によると、転職を考えたことがある人のうち 約3割が「行動できなかったことを後悔している」 と回答しています。
つまり「転職しようと思ったけど動けなかった」人の多くが、数年後に「あのとき挑戦しておけばよかった」と悔やんでいるのです。
また、マイナビ転職の「転職動向調査 2025年版(2024年実績)」では、転職の理由の第1位は「給与が低かった(25.5%)」でした。
さらに、転職を決めた理由の第1位も「給与が良い(25.9%)」という結果になっています。
👉 これはつまり「給与への不満」が転職の動機になりやすい一方で、不満があっても「動けなかった人」が一定数存在し、後悔につながっていることを示しています。
2. 人生全般における後悔
心理学者トーマス・ギロヴィッチとビクトリア・メディベが1995年に行った研究では、後悔には時間的な特徴があることが示されています。
短期的には「やった後悔(行動して失敗した後悔)」の方が強く感じられますが、時間が経つにつれてその痛みは薄れていきます。失敗や恥ずかしさも、やがて「経験」や「学び」として整理されやすいからです。
一方で「やらなかった後悔(行動しなかった後悔)」は逆で、数年、数十年経っても消えにくく、むしろ心の中で大きくなる傾向があります。
実際、彼らの調査では 長期的に残る後悔のおよそ8割が「やらなかったこと」に関するもの であると報告されています。
3. 高齢者へのインタビュー調査
また、海外の調査でも興味深いデータがあります。
高齢者に「人生で最も後悔していることは何か?」と尋ねた調査では、圧倒的に多かった答えが 「挑戦しなかったこと」 でした。
- やりたいことを仕事にしなかった
- 行きたい場所に行かなかった
- 愛する人に気持ちを伝えなかった
こうした「行動しなかった後悔」が、晩年まで強く残り続けていることがわかります。
小まとめ
これらの調査や研究から見えてくるのは、「やらなかった後悔」は誰にでも起こり得る普遍的な感情であるということです。
さらに、その後悔は時間が経つほど強く残り、人生の節目や晩年になってから「もっと挑戦しておけばよかった」と思い返される傾向があります。
挑戦して失敗した後悔は経験に変わりますが、挑戦しなかった後悔は「もしも」の想像として残り続ける──。
データはその現実を裏付けているのです。
第5章:なぜ「やらなかった後悔」は長く残るのか
「やらなかった後悔」が長く心に残るのは偶然ではありません。
心理学的に見ても、それには明確な理由があります。ここでは代表的な3つのポイントを紹介します。
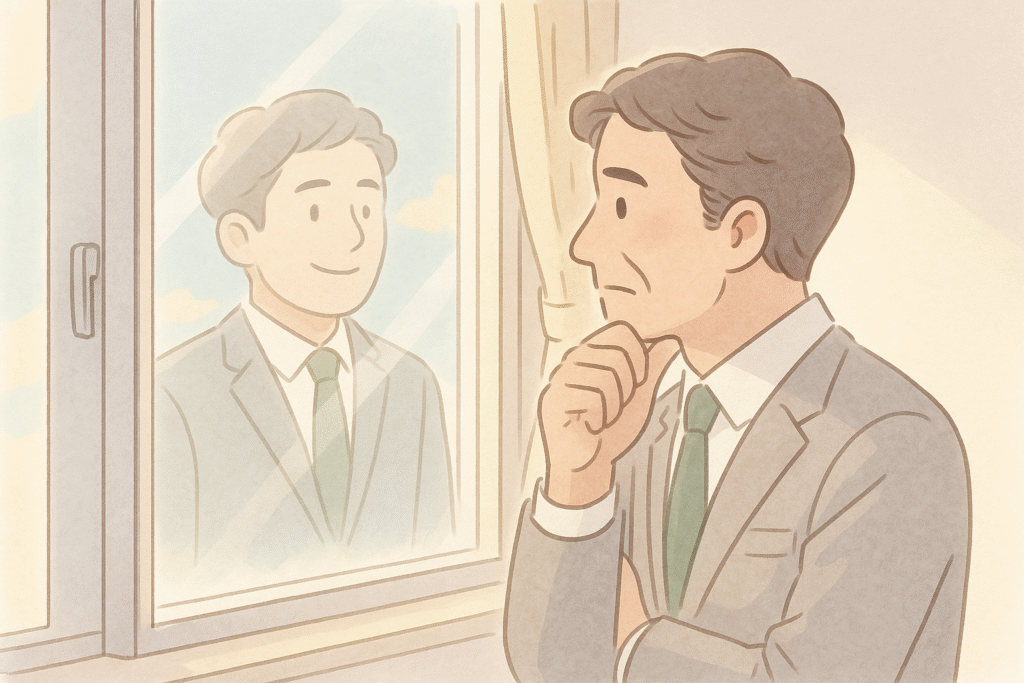
1. 「別の未来」を想像してしまうから
行動しなかった場合、実際に経験していないため「もう一つの可能性」が消えてしまいます。
この「もし挑戦していたら」という想像は、時間が経つほど理想化されていき、現実の自分と比較され続けるのです。
- 「留学していたら、もっと視野が広がっていたかもしれない」
- 「あの時告白していたら、今でも一緒にいられたかもしれない」
こうした「仮想の未来」は心理学で カウンターファクチュアル思考(If only…思考) と呼ばれます。
「もしあの時〜していれば」と繰り返し想像することで、後悔は薄れるどころかむしろ強まってしまうのです。
2. 記憶の美化効果
心理学には「記憶の美化」という現象があります。過去を振り返るとき、人は良い面を強調し、悪い面を忘れやすい傾向があるのです。
行動して失敗した場合は、「辛かった」「大変だった」という現実の記憶が強く残るため、時間が経つにつれて「あの失敗があったから今がある」と前向きに整理できることがあります。
しかし、行動しなかった場合は「挑戦していたらうまくいったかもしれない」という 成功した未来だけを都合よく想像してしまう のです。
結果として、現実の自分とのギャップが広がり、後悔がより強く心に残ります。
(例)
- 起業に挑戦せず安定を選んだ人は、「もし起業していたら成功していたに違いない」と思い込む
- 学生時代に告白できなかった人は、現実には失敗していた可能性を無視して「きっと上手くいったはず」と想像してしまう
3. 修正の余地がない
「やった後悔」には修正の余地があります。
失敗しても、次に挑戦したり学びを活かしたりすることで「やってよかった」と整理できるのです。
たとえば、転職して失敗しても再転職ができる、告白して失敗しても次の恋愛に活かせる、といった具合です。
一方で「やらなかった後悔」には、その経験そのものが存在しません。
やらなかった事実は取り返しがつかず、修正も学びも得られないため、心に残り続けるのです。
小まとめ
「やらなかった後悔」が長期的に強く残る理由は、
- 想像の中で理想化された未来が残る(カウンターファクチュアル思考)
- 記憶の美化によって「成功したかもしれない」と思ってしまう
- 修正や学びの機会がないため、解消されない
という3つの心理メカニズムにあります。
つまり、やらなかった後悔は 「未来への未練」と「過去への執着」が絡み合って生まれる、非常に根深い感情 なのです。
第6章:やらなかった後悔を減らすための考え方
「やらなかった後悔」が長く残ることは、心理学の研究からも明らかになっています。
では、私たちはどうすれば「やらなかった後悔」を減らし、自分の選択に納得できるようになるのでしょうか?
ここでは日常に取り入れられる3つのヒントを紹介します。

1. 小さな一歩から始める
大きな決断をいきなりしようとすると、人は不安や恐怖で足がすくみやすいものです。
そこで有効なのが「小さな一歩」を踏み出すことです。
- 転職が不安なら、まず転職サイトに登録してみる
- 留学がハードルなら、短期の語学研修から始める
- 告白が怖いなら、まず相手に感謝を伝えてみる
行動を「分割」して小さくすれば、不安を最小限に抑えつつ経験を積むことができます。
この小さな一歩が、未来の「やらなかった後悔」を防ぐきっかけになるのです。
心理学的にも「行動活性化(Behavioral Activation)」と呼ばれる手法があり、行動を小さく刻んで始めることで不安が減り、成功体験が積み重なりやすいとされています。
2. 未来の自分に問いかける
「今この選択をしなかったら、5年後、10年後の自分はどう感じているだろう?」
未来視点で考えると、目先の不安よりも「挑戦しなかったことへの後悔」が浮き彫りになります。
行動経済学の研究(ダニエル・カーネマンら)では、人は「短期的な利益や目先の安心」に流されやすく、長期的に合理的な判断をするのが難しいことが示されています。
だからこそ、私たちは「今動かない方が安全」と思い込んでしまいやすいのです。
一方で、未来の自分を意識することで長期的な選択が改善される という研究もあります。
心理学者ハル・ハーシュフィールドの実験では、参加者に「年老いた自分の顔」をVRで見せると、将来のための貯蓄や長期的な行動を選ぶ割合が増えることが報告されています。
つまり「未来の自分を想像すること」は、短期的な不安よりも「やらなかった後悔」をリアルに感じさせ、行動の背中を押してくれるのです。
3. 「失敗しても学びになる」と捉える
「失敗=悪いこと」という考え方が、私たちの行動を妨げます。
しかし実際には、失敗は貴重な学習の機会です。
- 挑戦した → うまくいかなかった → でも経験が残る
- 挑戦しなかった → 何も残らず、後悔だけが積み上がる
この違いは非常に大きいのです。
「やらなかった後悔」が長く残るのは、失敗から得られる学びすら持てなかったから。
だからこそ「失敗してもプラスだ」と思えるようになると、自然と行動が選べるようになります。
小まとめ
「やらなかった後悔」を減らすには、
- 大きな決断ではなく小さな一歩を踏み出す
- 未来の自分に問いかけてみる
- 失敗すらも学びとして受け止める
この3つの視点を持つことが大切です。
行動そのものが「後悔を減らす最良の方法」になります。
だからこそ大事なのは、完璧な選択を探すことではなく、「自分の選択を信じて一歩を踏み出すこと」 なのです。
第7章:まとめ
本記事では、「やらなかった後悔」がなぜ私たちの心に強く残るのかを見てきました。
- 第1章 では、「やった後悔」と「やらなかった後悔」の違いを整理しました。
- 第2章 では、損失回避や現状維持バイアスといった心理学的なメカニズムを紹介しました。
- 第3章 では、学生時代・社会人・人間関係など、誰もが経験しやすい「やらなかった後悔」の具体例を挙げました。
- 第4章 では、調査データから多くの人が「やらなかった後悔」を抱えている現実を確認しました。
- 第5章 では、なぜその後悔が長期的に残り続けるのかを、心理的メカニズムから解説しました。
- 第6章 では、やらなかった後悔を減らすための考え方として、「小さな一歩」「未来視点」「失敗を学びに変える」という実践的なヒントを紹介しました。
こうして振り返ってみると、「やらなかった後悔」は誰にでも訪れる普遍的な感情であり、しかも時間が経つほどに心に重くのしかかることがわかります。
だからこそ大切なのは、完璧な選択を探すことではなく、「自分のやりたいように、自分の選択を信じること」 です。
後悔は生きていくうえで避けられないものですが、どんな後悔を抱えるかは自分で選ぶことができます。
「やらなかった後悔」よりも「自分を信じて行動した後悔」を選ぶ方が、未来の自分にとって価値ある経験になるはずです。
あなたはどちらを選びますか?
- やらなかった後悔を抱え続ける人生
- それとも、自分の選択を信じて一歩踏み出した人生
未来の自分が笑顔で振り返れるように、今できる小さな一歩 を踏み出してみましょう。