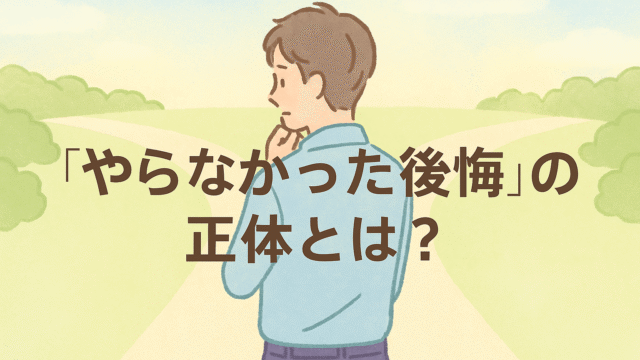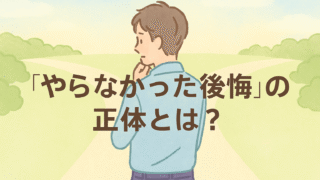「10年後のあなたが後悔しているのは、転職したことではなく──転職しなかったことかもしれません。」
「もしあの時、転職していたら──」
ふとした瞬間にそんな思いが頭をよぎったことはありませんか?
「転職したいけど、不安で動けない」
「思い切って転職したけれど、思っていたのと違った」
これは、多くの人が一度は抱える悩みです。キャリアの選択は人生を大きく左右するからこそ、迷いと後悔はつきものになります。
心理学者トーマス・ギロヴィッチとビクトリア・メディベ(1995)の研究では、短期的には「やった後悔」が強く感じられるものの、長期的には「やらなかった後悔」が強く残りやすいことが明らかになっています。
つまり転職においても、「挑戦しなかった自分」を後悔し続ける可能性が高いのです。
私自身も、調理師として働き始めた頃、「本当にこの道でいいのか」と悩みながらも安定を理由に行動できずにいた時期がありました。朝から晩まで厨房に立ち続けながら、「このままでいいのだろうか」と自分に問いかけていた日々は、まさに「やらなかった後悔」につながりかけていたと思います。
一方で、勇気を出して転職したものの「こんなはずじゃなかった」と後悔する人もいます。しかし、その失敗から新しいキャリアを切り拓いた人は少なくありません。
では、あなたは「やらなかった後悔」と「やった後悔」、どちらを選びますか?
この記事では、心理学的な裏付けと実際の事例をもとに、この問いの答えを一緒に考えていきます。

それではまず、「転職しなかった後悔」について、その心理背景や具体的な事例を見ていきましょう。
Contents
第1章 転職しなかった後悔とは
「今の仕事に満足していない」
「やりたいことはあるけど、安定を手放すのが怖い」
そう思いながら行動できないとき、私たちは「転職しなかった後悔」を積み上げていきます。
第1章:転職しなかった後悔
心理的背景
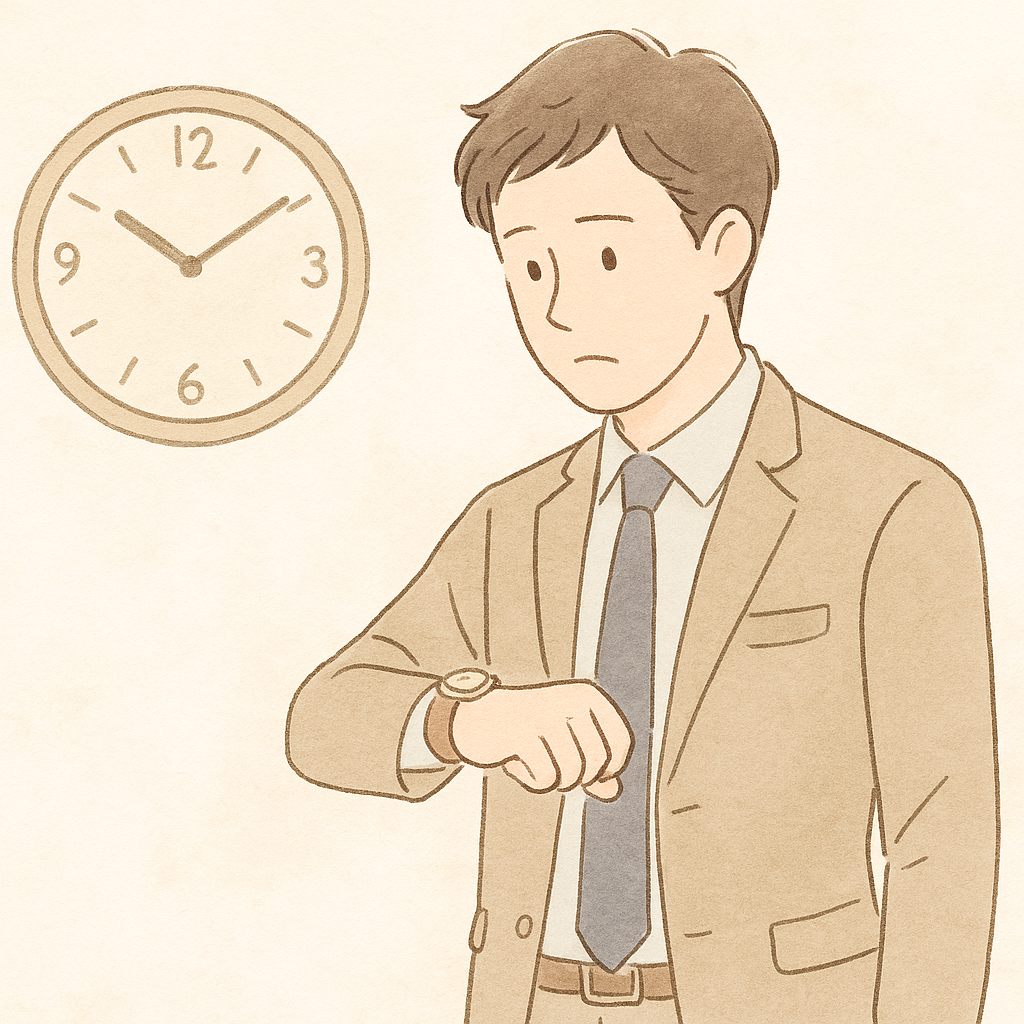
転職したい気持ちはあるのに、
「今の環境を捨てるのは不安」
「もし失敗したらどうしよう」
と考えてしまい、一歩を踏み出せない人は多いです。
その背景には、心理学的なメカニズムがあります。
- 損失回避(Loss Aversion)
人は利益を得る喜びよりも、損失の痛みを2倍以上強く感じるといわれます。
たとえば、月収が5万円増える喜びよりも、5万円減る恐怖の方が心に大きく響くのです。 - 現状維持バイアス(Status Quo Bias)
「変わらない方が安全」と感じる心理です。多少の不満があっても「慣れている職場」に留まろうとします。 - サンクコスト効果(埋没費用効果)
「せっかく10年勤めたのだから」「資格を取ったのだから」と、これまでの投資を無駄にしたくない気持ちが現状に縛り付けます。 - 後悔回避理論(Regret Aversion)
「もし行動して失敗したらどうしよう」という未来の後悔を恐れる心理です。しかしその結果、行動しなかった後悔を長期的に抱えることになります。
これらの心理的バイアスが重なることで、人は転職を考えながらも行動できなくなってしまうのです。
日常に潜む「やらなかった後悔」
こうした心理的傾向は、日常の小さな場面でも現れます。
- 求人サイトを開いて気になる会社を見つけても「自分には無理だろう」と閉じてしまう
- 上司に叱られ「もう辞めたい」と思っても、翌朝には同じ電車に揺られて出勤してしまう
- 飲み会で転職した友人の話を聞き「羨ましい」と感じながらも、自分は行動に移せない
このような小さな先送りが積み重なり、数年後に「なぜあの時動かなかったのか」と強い後悔につながっていきます。
実際のケース
① 年齢の壁に直面したケース
佐藤さん(仮名・38歳)は、30歳の頃から転職を考えていました。
「子どもが小さいから」「今は景気が不安定だから」と理由をつけて先延ばし。気づけば40歳目前。求人票には「35歳まで」の文字が並び、選択肢は大きく減っていました。
「挑戦するならもっと早く動いておけば…」
年齢という制約は、時間とともに後悔を強める要因となります。
② スキルを伸ばせなかったケース
田中さん(仮名・29歳)は、IT業界に憧れながらも安定した事務職を続けていました。「未経験では通用しない」と挑戦を諦めたのです。
しかし同年代の友人はエンジニアとしてキャリアを積み、収入も上がっていきました。30歳を目前にして、「あの時挑戦していれば」と強い後悔を抱くようになりました。
③ 家庭や環境を理由に諦めたケース
山本さん(仮名・42歳)は、住宅ローンや子どもの教育費を理由に転職を見送り続けてきました。
しかし体調を崩して退職を余儀なくされたとき、「もっと余力のあるうちに動いておけば」と深く後悔しました。
安全を選んだつもりが、結果的に大きな代償を払うことになったのです。
データが示す現実
リクルートワークス研究所の調査によれば、転職を希望しても行動できなかった人は少なくありません。その多くが後に「動かなかったことを後悔している」と答えています。
さらに、マイナビ転職「転職動向調査 2025年版(2024年実績)」によると、転職を始めた理由の第1位は 「給与が低かった(25.5%)」。
そして転職を決めた理由の第1位も 「給与が良い(25.9%)」 でした。
つまり、多くの人が「給与への不満」で転職を考え、「給与の改善」で決断します。
しかし、不安から行動できなかった人は「もし挑戦していれば」と後悔を抱えることになるのです。
小まとめ
「転職しなかった後悔」は、年齢・スキル・家庭環境にかかわらず誰にでも起こり得ます。
心理学的に人は「損失を避けたい」「現状を維持したい」と考えがちですが、その結果として 「もしあの時挑戦していれば」という後悔が長く残る のです。
あなた自身はどうでしょうか?
「給与や働き方に不満があるけれど、失敗が怖くて動けない」──そんな状況に心当たりはありませんか?
行動しなかった後悔は、静かに、しかし確実に未来の自分を苦しめます。
次章ではもう一つの側面、「転職して失敗した後悔」を見ていきましょう。
第2章:転職して失敗した後悔
「こんなはずじゃなかった」という現実
勇気を出して転職したのに、待っていたのは理想とはかけ離れた現実だった──。
これは珍しいことではありません。むしろ多くの人が一度は直面する壁です。
よくあるのは以下のようなギャップです。
- 仕事内容のギャップ
求人票に「裁量が大きい」とあっても、実際は雑務ばかりでスキルアップできない。 - 職場環境のミスマッチ
「風通しが良い会社」と聞いて入社したのに、上下関係が厳しく発言しにくい。 - 待遇の悪化
残業が増えたり、ボーナスが想定より低かったりして生活が苦しくなる。
転職は「より良い未来」を信じて挑戦するからこそ、その落差が強烈な後悔に変わるのです。
実際のケース
① 思っていた仕事内容と違ったケース
鈴木さん(仮名・32歳)は、スキルアップを期待してIT企業へ転職しました。
「最新の技術に触れられる」と面接で聞き、希望に胸をふくらませていました。
しかし、配属されたのは希望とは無関係の部署。与えられるのはエクセルの資料作成や庶務ばかり。
「これなら前職の方がよほど専門性を磨けたのでは…」と後悔が募りました。
② 職場環境が合わなかったケース
佐々木さん(仮名・28歳)は、「アットホームな社風」に惹かれて転職。
ところが入社してみると、上司のパワハラが横行し、社員は皆萎縮。相談窓口も形だけで、改善される気配はありません。
「会社の雰囲気は、入ってみないと本当にわからない」──これを痛感しました。
③ 年収・待遇が下がったケース
木村さん(仮名・35歳)は、家庭との両立を求めて転職しました。
「残業が少なく、収入も安定している」と説明を受けていましたが、実際は毎日終電。さらに基本給は前職より5万円低かったのです。
「もっと条件をしっかり確認すべきだった」
彼の言葉は、転職を検討する誰にとっても耳の痛い教訓です。
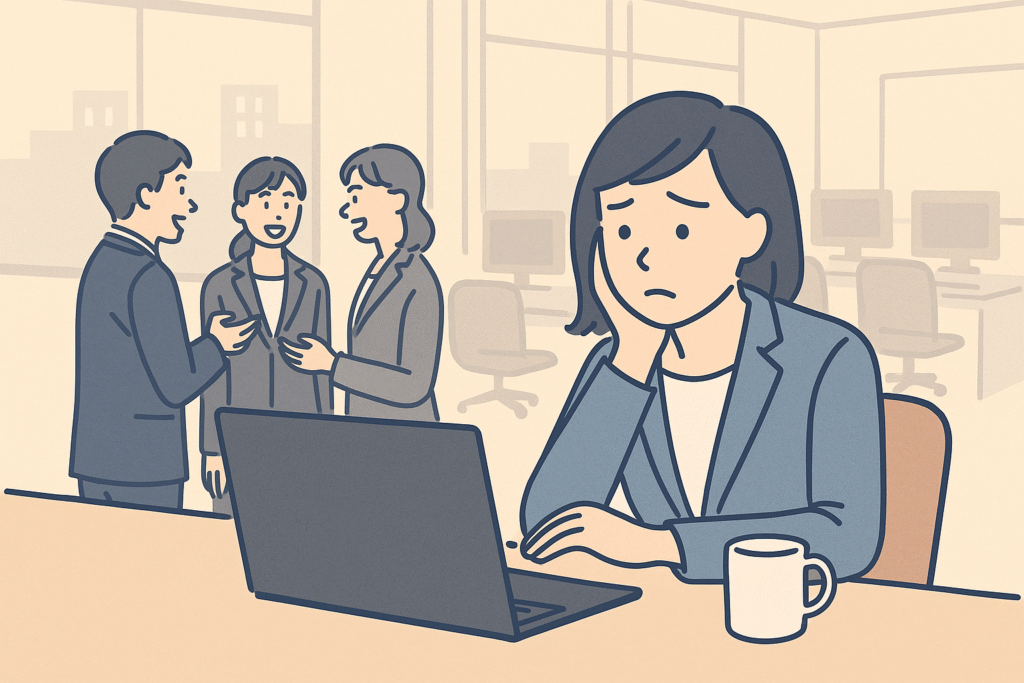
データから見る「転職失敗」
近年の調査では、入社後のギャップ(想定と現実のズレ) が、転職後の不満や後悔の大きな要因であることが示されています。
エン・ジャパンの調査によると、入社後にギャップを感じた人は約9割(87%) にのぼります。特にズレを感じやすいのは、
- 職場の雰囲気
- 仕事内容
という結果でした。
また、別の調査でも「ギャップがあった」と答えた人は 80% にのぼり、上位に挙がったのは同じく 「仕事内容」「職場の雰囲気」「仕事量」。
つまり「入ってみなければわからない部分」で不満を感じやすいことが明らかになっています。
さらにミドル層に関しては、転職コンサルタントの約4割が「入社後ギャップを感じる人が多い」と回答しており、その内容として 「人間関係」「仕事の進め方」「仕事内容」 が挙げられました。
待遇面に関しても注意が必要です。厚生労働省の統計によると、転職後に賃金が“減少”した人は28.9% にも上ります。
収入アップを期待して転職したのに逆に収入が減ってしまったケースも一定割合存在するのです。
これらの調査結果から見えてくるのは、情報収集や確認不足が「仕事内容/職場の雰囲気/仕事量・進め方/待遇」のミスマッチを招きやすい という事実です。
後悔の中から得られる学び
転職に失敗した後悔は、確かにその瞬間は辛く大きな痛みを伴います。
しかし時間が経つと、それは経験値となり、次のキャリア選択に活かされます。
- 仕事内容のギャップを経験した人 → 「自分はどんな業務にやりがいを感じるのか」が明確になる
- 人間関係に悩んだ人 → 「自分に合う職場環境」の基準を持てるようになる
- 待遇面で後悔した人 → 「条件交渉の重要性」を学び、次の転職に活かせる
「やって失敗した後悔」は、苦しみを伴いつつも自分を成長させる材料になるのです。
小まとめ
「転職して失敗した後悔」は、確かに一時的には強烈に心を揺さぶります。
しかしそれは 時間とともに学びに変わる後悔 です。
やらなかった後悔が「長く残る痛み」だとすれば、やった後悔は「次につながる痛み」だと言えるでしょう。境を選ぼう」という教訓を得られるのです。
第3章 心理学からの裏付け

後悔の心理 ― ギロヴィッチの研究
心理学者トーマス・ギロヴィッチとヴィクトリア・メドヴェックの研究(1995年, The 後悔の時間的な特徴
人は誰でも「後悔」を抱きます。しかし、心理学の研究はその後悔に 時間的な特徴 があることを示しています。
心理学者トーマス・ギロヴィッチとビクトリア・メディベ(1995)の研究によると:
- 短期的には「やった後悔(行動した後悔)」が強い
失敗や失言など「すぐに取り返しがつかない」と思える出来事が心に残りやすい。 - 長期的には「やらなかった後悔(行動しなかった後悔)」が強く残る
挑戦しなかった、告白できなかった、機会を逃した──といった「別の未来を試さなかったこと」が、時間の経過とともに強い後悔として意識される。
研究では、「長期的に人々が語る後悔の大半は“やらなかったこと”に関するもの」であることが明らかになっています。
つまり転職においても、短期的には「やって失敗した」ショックの方が強く感じられるものの、数年・数十年というスパンで残り続けるのは「挑戦しなかった後悔」である可能性が高いのです。
プロスペクト理論と後悔回避
ノーベル賞を受賞したダニエル・カーネマンらが提唱した プロスペクト理論 でも、人がリスクを避けて行動を先送りにする傾向が説明されています。
- 人は「利益」よりも「損失」を大きく評価する
- そのため「新しい挑戦で得られる可能性」より「失うかもしれない安定」の方が怖い
これが「転職したいけど動けない」心理の正体です。
さらに、後悔回避理論(Regret Aversion) も関連します。
「行動して失敗する後悔を避けたい」という気持ちが、結果的に「行動しなかった後悔」を生み出すのです。
選択のパラドックス
心理学者バリー・シュワルツが提唱した 選択のパラドックス も転職の迷いを説明してくれます。
現代は求人情報も多く、キャリアの選択肢も多様です。一見「選択肢が多いほど良い」と思われますが、実際には:
- 選択肢が多いほど人は決断に迷う
- 選択後も「もっと良い選択があったのでは」と後悔しやすい
転職市場はまさに「選択過多」の世界です。
これが「動けない不安」や「転職後の後悔」を強める要因となっています。
サンクコスト効果
もうひとつ重要なのが サンクコスト効果(埋没費用効果)。
「ここまで積み上げたキャリアを捨てるのはもったいない」
「資格を取ったのだから、この仕事を続けるべきだ」
この心理が、人を現状に縛りつけます。結果として、今の環境に不満があっても転職に踏み出せず、「やらなかった後悔」を深めてしまうのです。
小まとめ
心理学の研究からも、
- 短期的に強いのは「やった後悔」
- 長期的に残るのは「やらなかった後悔」
であることが明らかになっています。
さらに、人間には「損失を避けたい」「現状を維持したい」「積み上げを無駄にしたくない」という心理的なクセがあります。これが転職をためらわせ、後の人生に深い後悔を残すのです。
第4章:ケーススタディ ─ 人生の選択と後悔
転職における後悔は「やらなかった後悔」と「やった後悔」の両方に存在します。ここでは、実際によくある3つの選択軸── 年収・やりがい・家庭 ──を優先した人たちのケースを紹介します。
ケース① 年収を優先した人
高橋さん(仮名・33歳)は、結婚を機に「もっと収入を上げたい」と考え、大手メーカーから外資系企業へ転職しました。
転職によって年収は150万円アップ。ボーナスも前職の2倍以上になり、生活は安定しました。
しかし、彼を待っていたのは激しい成果主義の世界。ノルマに追われ、深夜残業や休日対応が当たり前。
気が付けば、子どもが寝てから帰宅する日々が続きました。
「収入は増えたけど、家族と過ごす時間は減った」
そんな思いが強くなり、ふと「前職にいた方が幸せだったのでは」と後悔することもあったそうです。
👉 このケースが示すのは、収入アップは目に見える成果だが、時間や生活の質とのトレードオフが生じやすいということです。
ケース② やりがいを優先した人
中村さん(仮名・29歳)は、広告代理店で働いていました。給与水準は悪くありませんでしたが、日々の業務は単調で「自分のクリエイティブ力を活かしたい」という思いを募らせていました。
思い切ってスタートアップ企業に転職し、やりがいのある企画職に就きました。
収入は前職より50万円ほど下がったものの、裁量権が大きく、日々新しい挑戦に取り組むことができました。
ただし、ベンチャーならではの不安定さもあり、資金繰りや業績不振によるプレッシャーは大きくのしかかります。友人から「安定を捨てて大丈夫なの?」と心配されるたびに、不安が頭をよぎります。
それでも彼女は言います。
「後悔がゼロなわけじゃない。でも“やらなかった後悔”よりは、挑戦できた後悔の方が納得できる」
👉 このケースが示すのは、収入や安定を失っても「やりがい」を得ることで心の満足感は得られる ということです。
ケース③ 家庭を優先した人
山田さん(仮名・40歳)は、子どもが小学校に入学するタイミングで転職を考えていました。
「子どもとの時間を大切にしたい」という思いから、残業が少なく、在宅勤務制度が整った中堅企業に転職しました。
前職と比べて年収は100万円近く下がり、キャリアの幅も狭まったと感じることもあります。昇進スピードも遅くなりました。
それでも、子どもの行事に参加できたり、家族で夕食を囲む時間が増えたりと、生活の満足度は確実に上がりました。
「収入や肩書よりも、今は家庭が最優先。その選択に後悔はない」
彼の言葉には、価値観の明確さが後悔を小さくすることが表れています。

ケーススタディから見えること
これらのケースからわかるのは、どの選択にも「プラス面」と「後悔の芽」が存在するということです。
- 年収を優先した人 → 収入は得たが、時間や心の余裕を失った
- やりがいを優先した人 → 安定は失ったが、自己実現の満足感を得た
- 家庭を優先した人 → キャリアの幅は狭まったが、生活の幸福度を高めた
つまり後悔を最小限にするには、「自分が何を優先するのか」を明確にしたうえで選択することが不可欠です。
第5章:後悔を減らすための考え方
転職における後悔を完全になくすことはできません。
しかし、心理学の知見と具体的な行動を組み合わせれば、「後悔を最小限にする」ことは可能です。
未来視点で考える
心理学の研究では、人は「今の快・不快」に強く影響され、未来の自分の気持ちを過小評価する傾向があるとされています。
たとえば「今は安定しているから動かない」という選択は、短期的には安心を与えてくれます。
しかし5年後・10年後に振り返ったとき、「なぜ挑戦しなかったのか」と後悔が大きくなるかもしれません。
👉 決断に迷ったときは、次の問いを自分に投げかけてみましょう。
- 「5年後の自分は、この選択をどう評価しているだろうか?」
未来の自分の視点を持つことで、短期的な恐怖に左右されにくくなります。
小さな一歩から始める

「転職」という言葉が重く感じるのは、いきなり大きな決断を迫られているように思えるからです。
しかし実際には、小さな行動の積み重ねが後悔を減らす第一歩になります。
具体的には:
- 転職サイトで求人をウォッチしてみる
- 転職エージェントに「相談」だけしてみる
- LinkedInで同業界の人とつながり、情報収集する
- 興味のある資格やスキルを少し学び始める
これらは「今すぐ会社を辞める」必要のない行動です。
それでも行動することで「もし挑戦していれば」という後悔を減らすことにつながります。
自分に問うべき3つの質問
後悔を減らすためには、自分の価値観を明確にすることが不可欠です。
その整理に役立つ3つの質問を紹介します。
- 「5年後、この選択を後悔していないか?」
短期的な安定より、未来の自分の満足を基準に。 - 「自分が本当に守りたいものは何か?」
年収か、やりがいか、家庭か。優先順位をはっきりさせる。 - 「それは誰かの正解ではなく、自分の正解か?」
周囲の価値観や常識ではなく、自分にとっての幸せの基準で考える。
これらを意識するだけで、選択の迷いは大幅に減り、後悔しにくい決断ができます。
実際の行動プラン例
後悔を減らすために、次のようなステップを踏むとよいでしょう。
- 現状の棚卸し
収入・やりがい・人間関係・家庭とのバランスを数値化してみる。 - 未来をイメージ
「このまま10年経ったらどうなるか?」を書き出してみる。 - 情報収集
転職サイトや口コミサイト、エージェントに相談して現実の市場を知る。 - 小さな行動
資格の勉強を始める、副業を試す、面接練習だけしてみる。
このように段階を踏めば、「動けなかった自分」という後悔は確実に減らせます。
小まとめ
後悔を減らすために重要なのは、未来視点を持ち、小さな行動を重ね、自分の価値観に基づいて選択することです。
大きな決断をしなくても、「情報を集める」「小さな一歩を踏み出す」という行動が、未来の後悔を静かに減らしていきます。
第6章:まとめ ─ あなたはどちらの後悔を選びますか?
ここまで「転職しなかった後悔」と「転職して失敗した後悔」について見てきました。
心理学の知見や事例、データを振り返ると、次のことがわかります。
1. 転職しなかった後悔
- 心理的背景:損失回避、現状維持バイアス、サンクコスト効果が「挑戦しない選択」を強める
- 現実の声:年齢・スキル・家庭などを理由に動けず、後に「なぜあの時…」と悔やむ人は多い
- 調査データ:行動できなかった人の多くが、後になって後悔を抱えている
👉 行動しなかった後悔は、静かに、しかし長期的に心に残るという特徴があります。
2. 転職して失敗した後悔
- 実際の失敗例:仕事内容のギャップ、人間関係の不一致、待遇悪化
- データ:入社後にギャップを感じた人は8割以上、賃金減少した人も約3割
- 学び:やった後悔は苦しくとも、経験として次のキャリアに活かせる
👉 転職に失敗した後悔は一時的には大きな痛みになるが、やがて学びに変わることが多いのです。
3. 心理学からの裏付け
- ギロヴィッチ&メディベの研究:短期的には「やった後悔」が強いが、長期的には「やらなかった後悔」がより強く残る
- プロスペクト理論:人は「得られる利益」より「失う不安」を大きく感じる
- 選択のパラドックス:選択肢が多いほど決断できず、後悔が強くなりやすい
👉 科学的にも、「挑戦しなかった後悔」の方が人生に深く残ることが示されています。
4. ケーススタディの示すもの
- 年収を優先した人:収入を得ても時間や心の余裕を失うことがある
- やりがいを優先した人:安定を失っても、満足感を得ることができる
- 家庭を優先した人:キャリアの幅は狭まるが、生活の幸福度を高められる
👉 正解は一つではなく、「自分にとって何を優先すべきか」を明確にしているかどうか が後悔の度合いを決めます。
5. 後悔を減らすための考え方
- 未来視点を持つ:「5年後の自分はどう感じるか?」を問いかける
- 小さな一歩を始める:情報収集・相談・スキル習得といった低リスク行動から着手
- 自分に問う3つの質問
- 5年後、この選択を後悔していないか?
- 本当に守りたいものは何か?
- 誰かの正解ではなく、自分の正解を選べているか?
👉 行動の大小にかかわらず、「やらなかった後悔」を減らすことはできるのです。
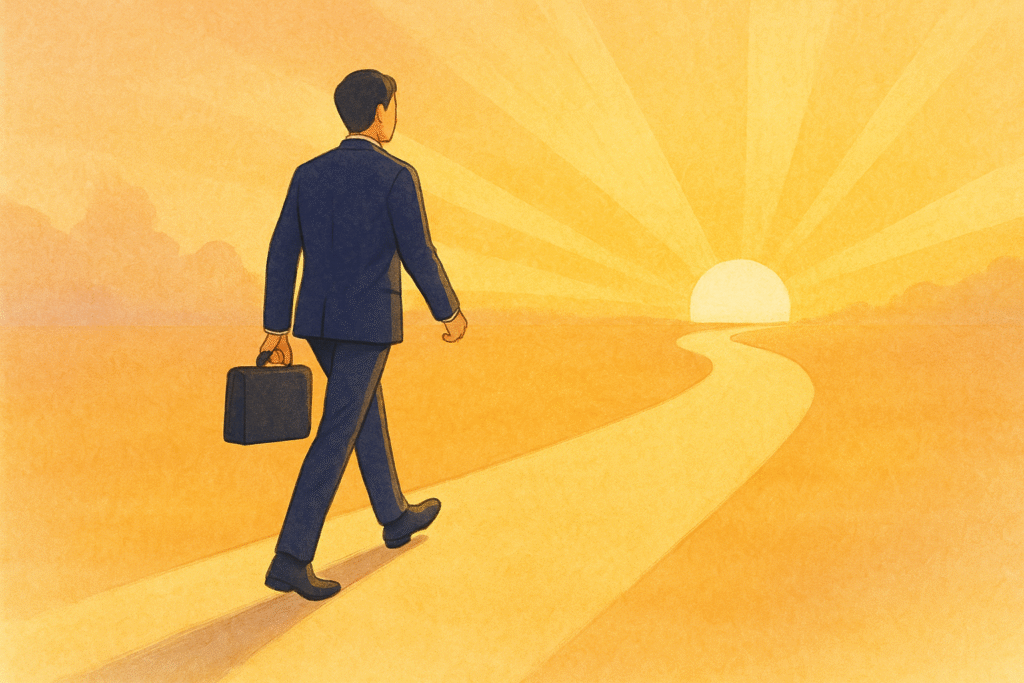
最後に
転職における後悔には、
- 行動しなかった後悔(長期的に心に残る痛み)
- 行動して失敗した後悔(一時的な痛みで、学びに変わる可能性が高い)
の2つがあります。
あなたは、どちらの後悔を選びますか?
もし迷っているなら、まずは小さな一歩から始めてみてください。求人サイトを眺める、転職エージェントに相談する、スキルの勉強を始める──。それだけでも未来の自分の後悔を減らせるはずです。
「やらなかった後悔」よりも、「自分を選んだ後悔」を。
その選択こそが、あなたの人生を前に進める力になるのです。